【ローカル役であがりたい方必見】麻雀ローカル役・役満10選徹底解説!

麻雀愛好家の皆さん!中には麻雀を始めたての方もいるかもしれません。
とにもかくにもこの記事を見ていただいているということは、皆さん、このような思いを抱いていることと思います。
「ローカル役ってよく聞くけど一体何?」
「ローカル役ってどんな役があるんだろう」
「麻雀でローカル役を上がってみたい!」
そこで!今回この記事では、麻雀のローカル役についてのこれらの問いに対して、徹底的にお答えしていきます!
また、記事の最後では、麻雀アプリ雀魂(じゃんたま)でのローカル役ありのルールの設定方法についてもお伝えします。
是非最後まで見ていってくださいね!
目次
1.麻雀のローカル役とは
2.有名な麻雀ローカル役・役満10選!
3.ローカル役を逃さないためのコツ!
4.雀魂でローカル役ありにする設定方法!
5.まとめ
1.麻雀のローカル役とは
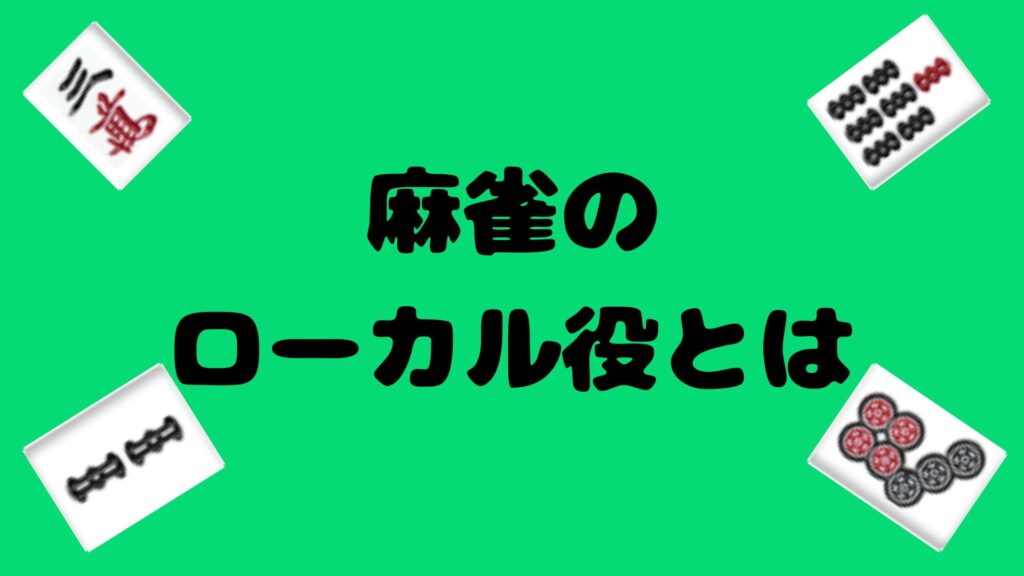
Wikipediaでは、麻雀のローカル役を「現在の日本の標準的な麻雀において正規には採用されていないが、一部のローカルルールで採用されている役、およびかつて採用されていた役」と説明されています。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、つまりは、あまり一般的ではない役という意味です!
出典 :「麻雀のローカル役」『フリー百科事典 ウィキペディア(Wikipedia)』。2024年11月21日 (木) 13:26 UTC、URL:https://ja.wikipedia.org/
ローカル役は中国由来の役や日本で独自に考案されて広まった役、他の地域を起源とする役など成り立ちは様々です。次の章では、その一部をかいつまんでご紹介します!
2.有名な麻雀ローカル役・役満10選!
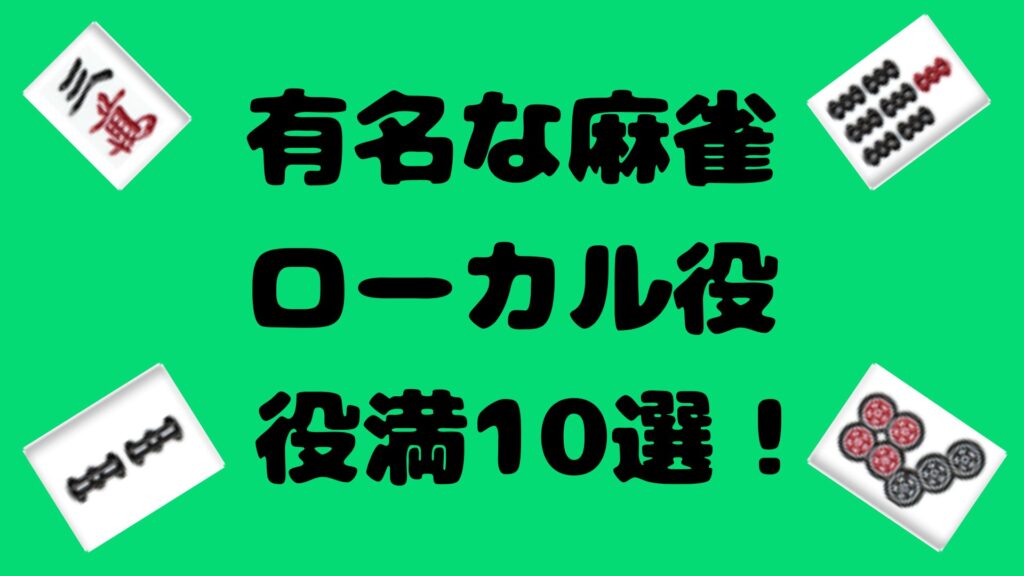
2-1.オープン立直(1翻)
リーチを宣言する際に、手牌を全員に見える形で公開することで成立する役です。
必ず、リーチ(1翻)と複合するため、2翻以上が確定します。
オープン立直が他家から掛けられた場合、待ち牌を全員が分かっている状態なので通常は誰も振り込みません。なので、万が一手牌にアタリ牌しかなく、やむを得ず振り込んでしまった場合は、役満として計算されます。
2-2.燕返し(1翻)
他家のリーチ宣言牌で自身がロンすることで成立する役です。
過去には、リーチをした人がリーチ後にツモ切った牌をロンしてあがることで成立する役として定義されていた時もありました。現在では、一般的に上記の定義に則って扱われます。
2-3.十二落抬(1翻)
難しい漢字が含まれていますが、この役は”しーあるらおたい”と読みます。
十二落抬は、4面子を全て鳴いて裸単騎の状態であがることで成立します。
麻雀初心者の方は、ついついポンとかチーとかをして鳴きすぎてしまうと思います。そのため、鳴きまくることであがれるこの役は、初心者がいる卓で採用することを非常におすすめします!
(例)3の萬子があがり牌の場合

2-4.五門斉(5翻)
こちらも初見で読むのはかなり厳しいと思いますが、”うーめんさい”もしくは”うーめんちー”と読みます。
五門斉は、萬子、索子、筒子、風牌、三元牌を全て使ってあがることで成立する役です。
ただしこの役の定義は非常に曖昧であり、トイトイ形で成立した場合のみ認めるルールや、雀頭は字牌以外認めないとするルール、面前でのあがりのみを認めるルールなど様々あり、この役のこれといった成立基準は定められていません。
(例)

2-5.石の上にも三年(役満)
ダブル立直(1順目で立直を宣言)した後、その局の自身の最後のツモであがることで成立する役です。地域によっては、最後の捨て牌をロンしてあがることでも成立します。
麻雀アプリ「じゃんたま」でもこの役は実装されていて、そこでは、ダブル立直をした上で自身の最後のツモであがるか、もしくは最後の捨て牌をロンするかで成立します。実際この役をあがることは非常に困難で、またほぼ運まかせであるため、あがるためには途轍もない運量が必要となります。
2-6.紅一点(役満)
役満である緑一色の發を中に置き換えることで成立する役です。
一面緑色の中に赤色の”中”の刻子が1セットだけ含まれる形なので、役の名称通りで非常に分かりやすいですね!
(例)

2-7.十三不塔(役満)
親は配牌時、子はポン・チー・カンのない第1ツモ時に、雀頭が1つのみであり、かつ面子(順子、刻子、槓子)や塔子(後1枚で順子となる形)が一切ない状態の場合に成立する役です。
手牌が非常にバラバラであったとき、通常の役を目指してあがることは難しいかもしれませんが、「実は十三不塔だった!」なんていう一発逆転のオチが起こるかもしれないそんな役です。
(例)この場合は南が雀頭

2-8.大車輪(役満)
筒子の2から8までを、それぞれ2枚ずつ面前の状態で集めた時に成立する役です。見たまんま、大きな車輪がたくさんある状態で成立する役なのでこの名前になりました。
似たような役に小車輪という役があり、こちらは筒子の1から7、もしくは3から9を2枚ずつ集めることで成立します。小車輪もローカル役であり、大車輪と同じく役満として扱われる場合もあれば、倍満や跳満として扱われる場合もあります。
(例)

2-9.大竹林(役満)
大車輪と同じく2から8までを2枚ずつ、これを索子で作ったときに成立する役です。こちらも竹がたくさんあるあがり役であるため、大竹林という名前がつけられました。
(例)

2-10.大数隣
大シリーズ最後の大数隣です!こちらも同様に、2から8までを2枚ずつ、これを萬子で作ったときに成立する役です。
(例)

これら3つの大シリーズはいずれも連七対という役に集約されます。連七対とは、連なる7つの数をそれぞれ2枚ずつ集めた時に成立する役であり、大車輪、大竹林、大数隣が全て含まれるだけでなく、1から7を2枚ずつ、3から9を2枚ずつ集めた場合にも成立します。あがれるパターンが一気に増えるのでこちらの役の方がお得ですね!
では、次の章ではローカル役を逃さないためのコツについてお伝えしていきます!
画像出典(麻雀牌) : 「麻雀王国」。URL:https://mj-king.net/sozai/download/manzu2.html
3.ローカル役を逃さないためのコツ!
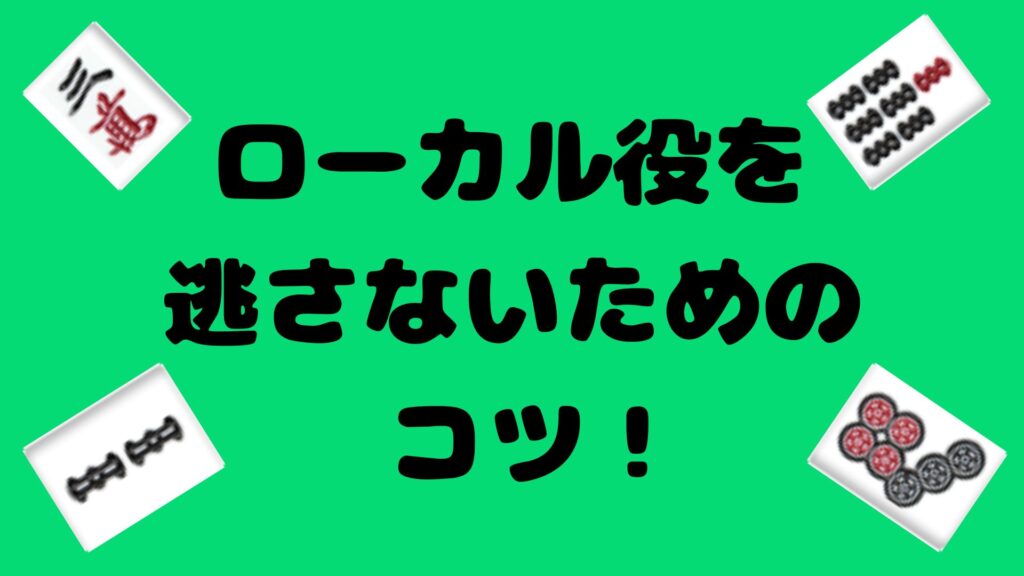
「麻雀でローカル役を上がってみたい!」
これは、この章を見てくださっている多くの方が抱いている気持ちであると思います。実際、ローカル役は知識として知っているだけではそう簡単にはあがれません。そこで!この章では、ローカル役をあがれるようになるためのコツについて詳しく解説していきます。
①どのローカル役が採用されているのかを確認する
まず大前提として、ローカル役をあがるためにはローカル役が採用されている雀荘、もしくは麻雀アプリで対局を行う必要があります。ご自身が普段通っている雀荘や使っている麻雀アプリがローカル役を採用しているのか、今一度確認してみてください。
その上で次は、採用されているローカル役を確認します。確認をしなければ、どのローカル役を狙えば良いのかの判断がつかないのはもちろんのこと、実際は採用されていないローカル役であがってしまってチョンボをくらってしまったり、麻雀アプリであがりボタンが表示されず、結果あがれなくなってしまったりする危険性があります。
そのため、自身の囲んでいる雀卓で採用されているローカル役を毎回常に確認するようにしましょう。
②初手の自分の配牌を見て狙えそうなローカル役を決める
上記にも述べたように、ローカル役は知識として知っているだけではそう簡単にあがれません。なぜならば、”組み立てへの意識”が欠如しているからです。
麻雀は、役作りの観点でのみ語れば”組み立て”のゲームです。手を組み立てて行く際、皆さんも「この役を狙おう」と考えながら打っているはずです。つまり、この役を狙おうという目的意識があって初めて、目的の狙っていた役へと辿り着けます。
要するに、「狙う役をあやふやにして手牌を組み立てていってはダメ!」ということです。
狙う役をあやふやにしたまま手牌を組み立てていっては、ローカル役へとは辿り着けません。それこそ、この章の目次にある通り、本来あがれるはずだったローカル役を逃してしまうことだってあります。
なので、初手の配牌を見て、ローカル役を目指せるのか目指せないのか、そしてローカル役を目指すのであればどのローカル役を目指すのかをご自身の中ではっきりさせてから打つようにしてください。
③具体的にどのローカル役ならあがれそうか考える
狙えそうなローカル役を決めるといっても、実際にどのローカル役があがれそうかなんて正直よく分からないですよね。
そこで、ここでは狙うのにオススメのローカル役について、主観ながら、簡単に述べておきます。
まず一つ目にあげたいのがオープン立直です。こちらは先ほどの、”2.有名な麻雀ローカル役・役満10選!”でも紹介しましたね。1翻であることもあり、比較的ほかのローカル役よりもあがりやすいと思います。立直の際に、全体に手牌を見せるだけで簡単に行えるため、最終形が多面待ちになった時や、他家があがれそうにない時に狙っておこなうのがオススメです。
次にオススメしたいのが十二落抬です。こちらはついつい鳴きすぎてしまう初心者の方が狙うのにオススメします。「鳴きすぎて役がない!」となっても一発逆転が狙えるのがこの役の良いところです。役がなくてあがれなくなってしまっても、打っている卓やアプリで十二落抬が採用されていないか、今一度確認してみてください!
最後にオススメするのが十三不塔です!こちらは2章にも書きましたがローカル役満です。ですが、通常の役満・ローカル役満よりも出る確率が非常に高く、1度麻雀プロリーグ戦(Mリーグ)でも出現したことがあります。この役は配牌時点で成立するため、いかにも手牌が不揃いであがれそうにない時には、もしかしたら十三不塔かも、と一度確認してみても良いかもしれませんね!
以上ここまで、ローカル役を逃さないためのコツについて順を追って詳しく解説していきました。まとめますと、
①どのローカル役が採用されているのかを確認する
②初手の自分の配牌を見て狙えそうなローカル役を決める
③具体的にどのローカル役ならあがれそうか考える
この3つを参考にして是非ともローカル役を実際にあがってみてくださいね!
ここまで読んでいただいた皆さんは、麻雀ローカル役のあれこれについて今まで以上に沢山知ってもらえたと思います。では最後にちょっとコラム的ではありますが、雀魂でローカル役をありに設定する方法について解説します!
4.雀魂でローカル役ありにする設定方法!
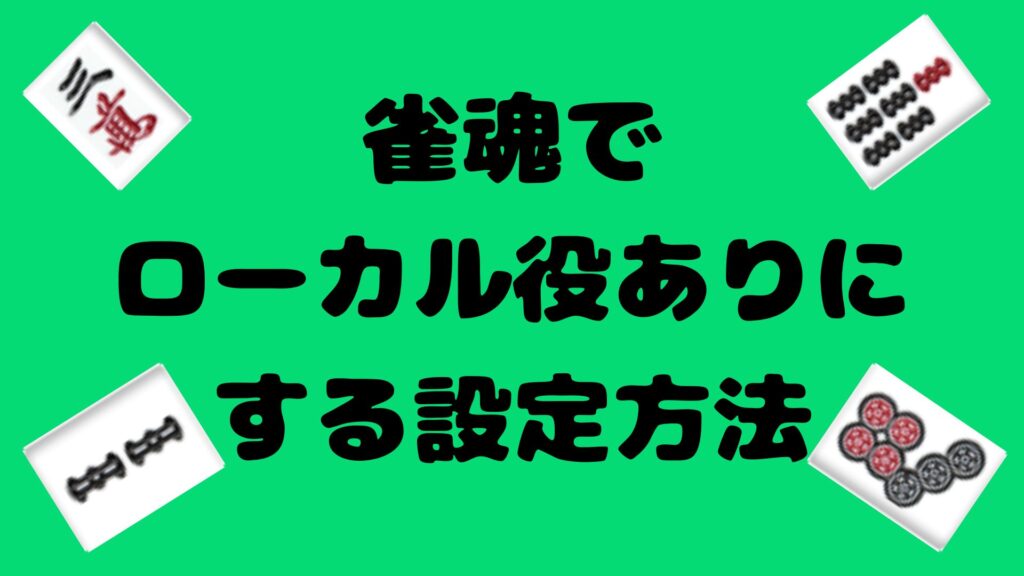
この記事を見ている方の多くはご存知かもしれませんが、有名な麻雀アプリの一つに「雀魂-じゃんたま-」というものがあります。実はこの雀魂にもローカル役が実装されています。
しかしながら雀魂は、段位戦やデフォルトの設定ではローカル役なしの状態で設定されているので、ローカル役ありに設定し直す方法が分からない、という方もいると思います。
そこで今回は、雀魂でローカル役をありにする設定方法について解説していきます!

まず画面を開いていただいたら、このような画面が表示されると思います。はじめに友人戦のところをクリックしてください!
(*段位戦はローカル役なしで設定されているので、ローカル役ありでプレイするためには友人戦、もしくは期間限定の大会戦で遊ぶ必要があります)

次にこのような画像が表示されると思うので、ルーム作成のボタンを押しましょう。
ルーム作成、ルーム参加は表示されている通り無料でプレイすることができます。

そしたらこのような画面が出てくると思うので、詳細設定を有効にしましょう!

すると、下に黄色の線が表示されますので、そこを下にスクロールしていったらローカル役の項目が見当たると思います。ローカル役のところを無効から有効へと変更しましょう。
そしたら作成ボタンを押してみましょう!

するとご覧の通り、ローカル役ありの状態で設定できました!
皆さんも友人と雀魂で打つ際は、ぜひローカル役ありでプレイしてみてください!戦略の幅が広がり、めったに見れないレアなローカル役があがれるかもです!
5.まとめ
・ローカル役とは、あまり一般的ではない役という意味
・1翻から役満までさまざまなローカル役が存在する
・ローカル役をあがるためには、どの役を目指すのか狙いを定めることが重要!
今回は、麻雀ローカル役のあれこれについて、いろいろと解説していきました。
この記事を読まれた皆さんは、読む前に比べて、麻雀ローカル役というものについて今まで以上に、より一層詳しくなれたのではないでしょうか。
ご存知の通り麻雀の世界はとても奥深いです。ローカル役にとどまらずさまざまなローカルルールや遊び方があります。なので、ローカル役以外にも是非いろんな遊び方を試して、ご自身の麻雀の世界を広げてみてください!きっと良い発見が見つかるはずです!
皆さんが良い麻雀ライフを送れることを心からお祈り申し上げます!
ここまでご覧いただき大変ありがとうございました!
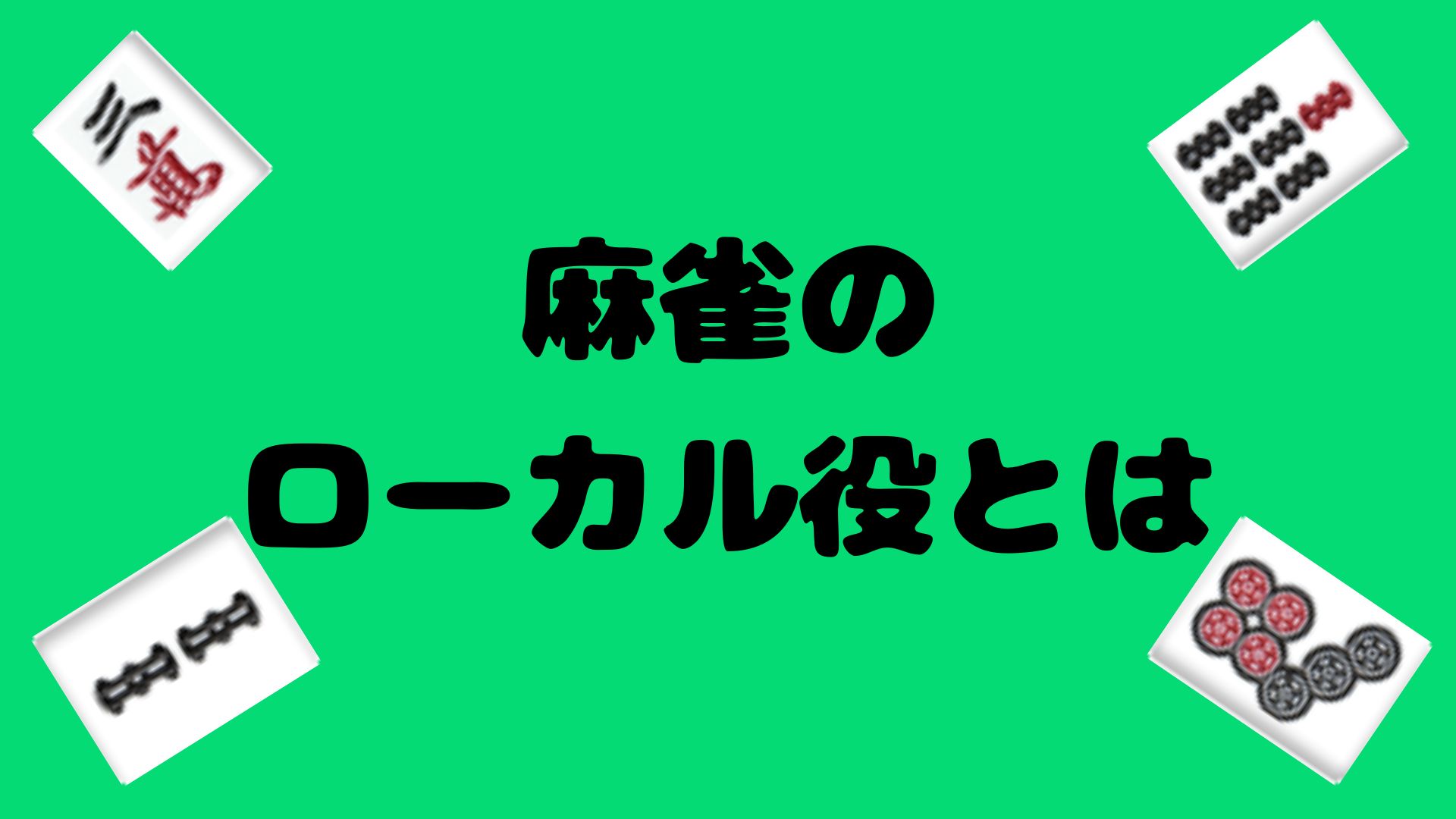
コメント